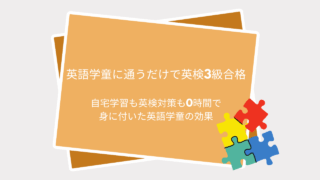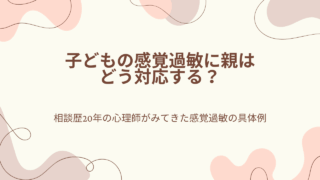はじめに
こどもが泣き喚いて大変…毎日でしんどい…
そんなご相談は多くあります。
些細なことがきっかけで、こどもが泣き喚くので、親の方もイライラしてしまう。
そんなこともありますよね。
「躾ができない親」と思われることが辛いというお話もよく聞きます。
子育ての中でみられることのある「癇癪(かんしゃく)」は、多くの方にとって大きな悩みのひとつです。
ここでは、癇癪の原因や対応、そして予防策についてご紹介します。
癇癪(かんしゃく)とは??
癇癪とは、こどもが感情をコントロールできずに泣き叫んだり、怒ったりする状態です。
これは、特に1~2歳の幼児期に多く見られ、5歳頃までには徐々に落ち着くとされています。
こどもの発達が心配な場合には、専門家に相談してみるのもひとつの手です。

使えるものは使って皆で子育てをよくできるといいですね
子育て支援センターってどんなところ?活用のメリットデメリットまとめ
癇癪はなぜ起こるのか??主な原因3つ
感情表現や感情コントロールの未熟さ
自分の感情を適切に表現することばや手段を持っていない、そうしたことが苦手な子もいます。
小学生になっても自分の気持ちや状況をうまく伝えられないことがあり、不満やストレスを癇癪として表現することがあります。
環境の変化やストレス
生活環境の変化や新しいできごとが苦手な子もいます。
それがストレスになって、些細なことをきっかけとして癇癪を起こすことがあります。
発達の特性
発達しょうがいや感受性の高さが、癇癪の頻度や強さに影響を与える場合があります。

癇癪=発達しょうがい、ではないし
発達しょうがいがあっても癇癪のない子ももちろんいます!
癇癪への対応のヒント3点
気持ちに名前をつけてみる
こどもが感じている気持ちに名前をつけることで、自分の状態への理解を深め、感情のコントロールを学ぶ手助けとなります。
例えば、怒っているの気持ちを「プンプンさん」と名付けるなど、こどもと一緒に考えると効果的です。

自分の気持ちを説明する練習にも繋がります
気持ちの切り替え方法を練習する
イライラしたときの対処法を、こどもが落ち着いているときに話し合い、練習しておくことが有効です。
例えば、イライラしたときには「大きく息を吸ったり吐いたりする」「静かな場所に行く」など、具体的な方法を決めておき、落ち着いているときにも練習してみます。

練習することが、実際の場面で役立ちます
おとなの対応を見直す
こどもの癇癪に対して怒鳴ったり、感情的に対応することは逆効果となる可能性があります。
冷静に対応し、少なくともこどもの感じていることに寄り添う姿勢は大切です。
おとなもイライラする気持ちに名前を付けて客観的に捉えてみたり、深呼吸をしたり、ときには、少し離れて落ち着けるよう休むなど、決めておいてもいいですね。

イライラしたら、怒鳴らずにトイレに行く!も有効だったりします
癇癪への予防策3点
一貫した関わり
日常生活でのルールやスケジュールに一貫性をもつことが、癇癪に繋げないための予防になります。
昨日は寝る前にチョコレート食べてよかったのに、どうして今日はダメって言うの?
今日も絶対食べたい!!!
と、こどもが感じて泣き喚いてしまうような場面はありませんか?

一貫しているとこどもは安心しやすくなります
よい行動を増やす
よい行動を取ったときには積極的に褒めます。
こどもが1日を過ごす時間は変わらないので、癇癪を起こさずによい行動をしている時間を増やせるといいですね。
そのためには、やはり褒めること。
敢えて素早く細かく褒めるとより有効です。
「すごい」「えらい」だけが褒めることばではなく、「片づけやってるね~」と伝えるだけでも十分なんです!

おとなが見てくれてる!と嬉しいのです
自己肯定感も育ちます!
コミュニケーションの促進
こどもが自分の気持ちをことばで表現できるように、日常的にコミュニケーションを取っておけるといいですね。
普段忙しい親御さんも、「1日10分だけこどもの話を否定せずに聞く」がおすすめです。
お風呂や寝る前の時間など、おうちの中で都合がよさそうな時間を決めてもいいですね。

〇〇って感じたんだね!と否定せずに伝えることで、自分の気持ちをことばで説明するモデルになります
専門家への相談
癇癪が長期化したり、日常生活に支障をきたす場合は、専門家への相談を検討しましょう。
児童精神科医や発達しょうがいの専門家が適切なアドバイスを提供してくれます。

ちょっと敷居が高いな…と感じる場合には、地域の子育て支援センターや小児科の先生に相談してみることもおすすめです
子育て支援センター行くべき?相談歴20年の心理師が伝える活用のメリットデメリットまとめ
まとめ
癇癪はこどもの成長過程でよく見られるものですが、適切な対応と環境調整により、その頻度や強度を軽減することが可能にもなります。
こどもの気持ちに寄り添いながら、おとなも一緒に成長していけるといいですね。
しんどいときは、たくさん周りに頼ってOK
社会みんなでこどももおとなも育まれるといいなと思います。