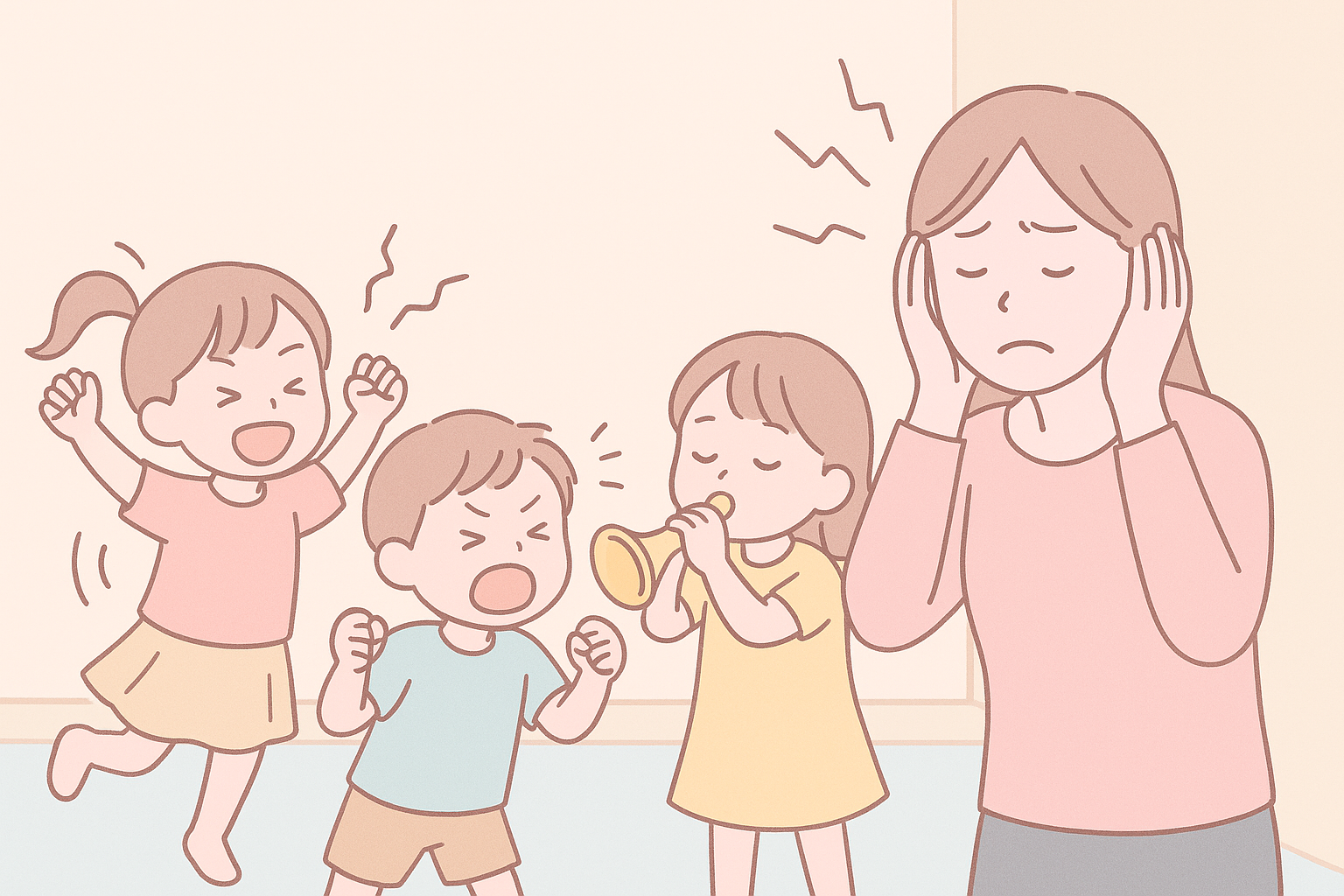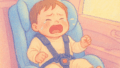はじめに
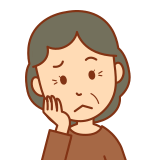
子どもの足音がうるさいと苦情が届きました。
うるさくしないようにと子どもに注意しすぎてしまい、子どもは癇癪を起こして悪循環になります。

そんなお悩みを聞くことは結構多いです。
集合住宅では、子どもの泣き声や足音が原因で近隣トラブルになることが少なくありません。
この記事では、引っ越し先を探す段階での注意点から、実際にトラブルが起きたときの対処(記録→話し合い→管理会社/自治体相談→防音対策)まで、現場で使える具体策をまとめました。
トラブルが起きやすい場面と背景
集合住宅の騒音トラブルで多いのは、「足音・走り回る音」「夜泣き・大声」「ドアの開閉や物の落下音」になります。
建物の構造(木造・軽量鉄骨は遮音性が低い)や生活リズムの違い、管理体制が不十分だと問題が深刻化しやすい点に注意が必要です。
いくつかの調査・専門家の指摘でも、建物構造や生活リズムが騒音トラブルの主因になっているとされています。
まずやるべき「事実の記録」と「穏やかな口調」
トラブル全般にいえることですが、トラブルへの対応は「感情のぶつかり合い」になってしまうと解決が遠のきます。
苦情が届いたときには、以下をまず実行してみましょう。
子どもの生活時間をメモする
子どもの帰宅時間や食事時間など一日の流れを大まかにメモしてみましょう。
集合住宅では苦情の実際が、別な階の騒音だった!というケースもあります。
苦情と照らし合わせるためにも、後で管理会社や自治体に提出できる証拠になることがあります。
苦情となった騒音の性質を整理
日常生活上致し方ないと思われる足音なのか、大きな泣き声なのか、きょうだいケンカや落下音なのか、整理してみましょう。
穏やかに話す
苦情が届くと、子どもや親としての自分が責められていると感じて悲しくなったり辛くなったり、または、相手方が神経質なクレーマーだと感じて怒りやイライラの感情が起こることがあります。
先述したように「感情のぶつかり合い」になってしまうと、問題解決が遠のいてしまいます。
相手方の言い分を冷静に聞いた上で、伝えられる事実は伝えられるように準備することが大切です。(例えば、苦情の実際の時間には在宅していなかった、など)
多くの相談事例や体験談でも、最初の穏やかな話で改善したケースが多く報告されています。
管理会社・大家・管理組合に相談する流れと法的ポイント
直接の話し合いでは改善しない、またはトラブル回避のため直接の話し合いは避ける方が望ましい場合、管理会社や大家(賃貸)・管理組合(分譲)へ相談しましょう。
管理側には入居者同士の生活環境を保つ義務があり、事実確認のうえで是正を求める対応を行うことが一般的です。
管理会社は両者の調整役として注意喚起や面談、実際の騒音の調査、最終的には契約解除などの措置を検討する場合もあります。
受忍限度(周囲が我慢すべき範囲)を越えているかどうかが重要な判断基準であるようです。公益社団法人 全日本不動産協会
相談先の順序(推奨)
-
当事者(近年は当事者同士の話し合いは避けるべきという考えもあります)
-
管理会社/大家/管理組合へ相談
-
自治体の公害・環境窓口、消費生活センターなどへ(証拠があると動いてもらいやすい)。

建物構造・時間帯・「受忍限度」の考え方(法律上の見解)
法律上、生活音すべてを禁止することは難しく、音の種類・時間帯・継続性などで「受忍限度(周囲が我慢すべき範囲)」を超えるかどうかが判断されます。
たとえば深夜の大声や長時間にわたる継続的な振動などは受忍範囲を超えると認定されやすい一方、日中の一時的な足音などは我慢の範囲とされるケースが多いようです。
判断には専門家(弁護士、建築士)の助言が有効になることがあります。公益社団法人 全日本不動産協会
具体的な防音対策5選
厚手カーペット・ラグや防音ジョイントマットを敷く
走り回りの音の衝撃を吸収してくれます。
対策の第1歩として取り掛かりやすく、実践する方が多いです。
家具を壁際に配置して音の拡散を抑える
隣宅と接する壁に家具を配置するなどして、音が伝わることを抑える効果があります。
可能な範囲で試してみる価値はあり、こちらも取り組んでみる方が多いです。
静音スリッパ/ルームソックスなどで足音を軽減
子ども用のルームスリッパやソックスがあります。
子どもが履いてくれるのであれば、こちらも試してみるとよいですね。
厚手カーテンで室内音の漏れを抑える
厚手のカーテンを取り付けることで、室内音の漏れを抑えられることがあります。
吸音パネルや壁面断熱材、床の二重床化工事
防音工事は効果が高い反面、費用負担と管理側の許可がハードルになります。
まずは簡易対策から試すことが現実的です。
子育て世帯としてできる工夫
地域資源を活用す
日中に児童館や公園を利用して、たくさん遊んで子どものエネルギー発散を促しましょう。
太陽の光を浴びて身体をたくさん動かすと、夜には早目にぐっすり眠ってくれることが増えます。
生活リズムを調整する
苦情のあった時間を考慮して、昼寝や遊びの時間帯を調整してみましょう。
静かに過ごせる時間を作れるよう、一日の流れを考えてみるとよいですね。
子育て支援センターや地域のファミリーサポートを利用する
一日の生活時間の工夫や、元気いっぱい体力有り余る子どもの遊び場所などについて、子育て支援センターに相談してみることもできます。子育て支援センター行くべき?相談歴20年の心理師が伝える活用のメリットデメリットまとめ
また、地域のファミリーサポートで一時預かりの相談ができることがあります。
近隣トラブルを避けるには「見える配慮」と「地域に参加する姿勢」が効果的なことが多いです。
それでもうまくいかないときには、親子の心身のストレスのために引っ越しを検討することも手です。

苦情が届くと親もストレスで、子どもを叱りすぎてしまうことがあります。
引っ越しを検討する場合には、一括査定でできるだけ負担を少なくしたいですね。
まとめ
集合住宅の騒音トラブルは「どちらが完全に悪い」という単純な構図になりにくく、双方の理解と管理側の適切な介入が解決の鍵になります。
まずは感情的にならず、順序立てて動くことをおすすめします。
親子が笑顔で健やかに過ごせる住環境になることを願っています。
参考リンク(相談窓口)
-
全日本不動産協会「アパートにおける騒音クレーム」解説。公益社団法人 全日本不動産協会