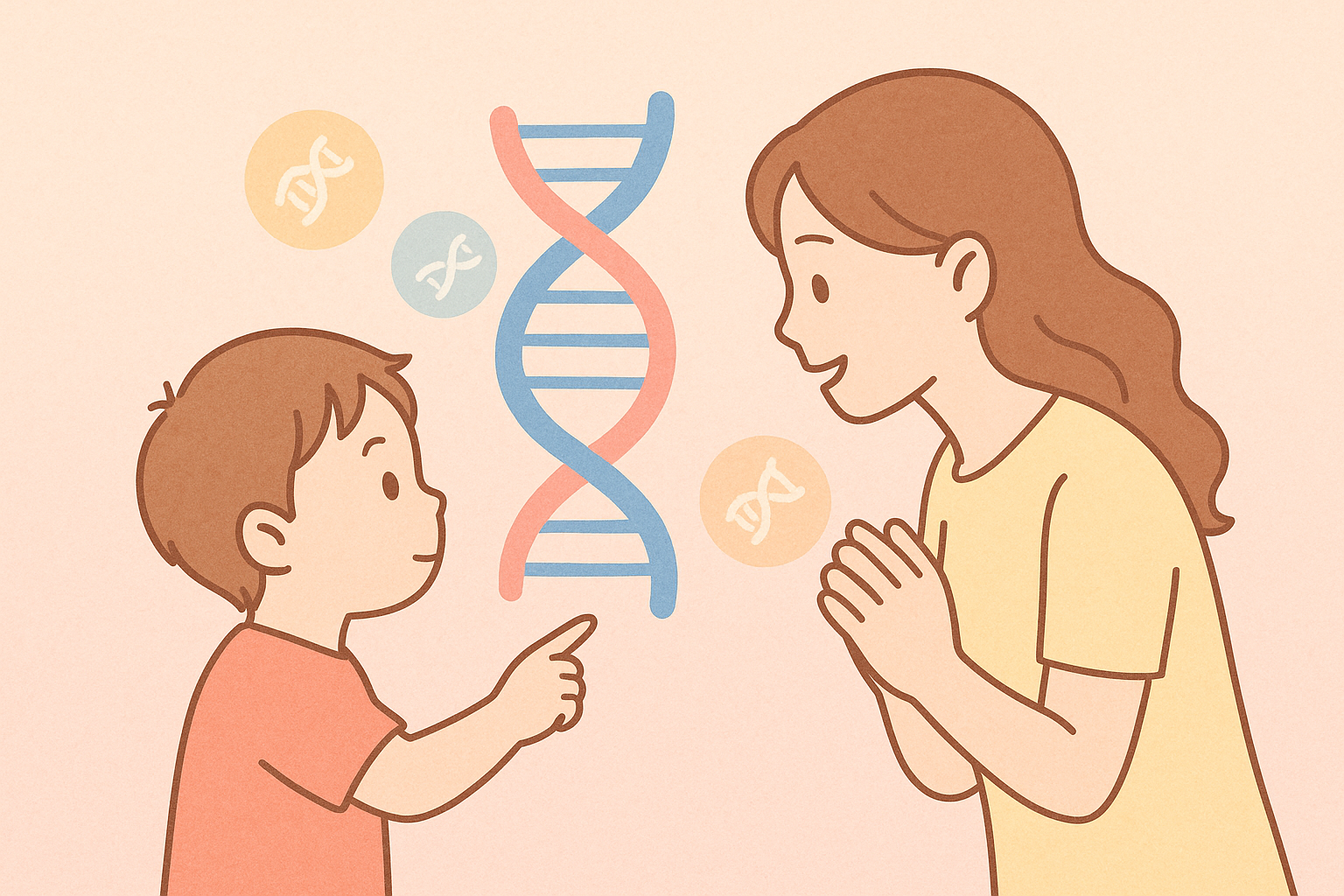はじめに
この記事では、「GIQ(ここでは「遺伝子情報から知能傾向を解析するタイプの市販のサービス」を指す総称)」を実際に試した体験の情報と、最近の研究や社会的な動向をまとめました。

保護者支援グループで話題に出たので、それを基にまとめてみました。

医学的な判断や教育方針は医師や専門家と相談してくださいね。

GIQって何?
GIQは「遺伝子(DNA)データをもとに、その人の認知傾向・学習適性・いわゆる『IQ』的素養の一部を推定する」――と謳うダイレクト・トゥ・コンシューマー(DTC)型の遺伝子解析サービスの総称としてこの記事では扱っています。
近年、海外や国内の企業が「DNAから得られる多くの遺伝子マーカーを統計的に組み合わせてスコア化する」商品を出していいて、個人向けに販売されています(日本でも遺伝子検査を提供する事業者が存在します)。
実際の申し込み:流れと所要時間
保護者支援グループで話題に出たサービスを基に、一般的な流れは以下の通りでした(サービスによって多少差があると思います)。
-
Webで申し込み・同意(利用規約・個人情報の扱いを確認)。
-
検体キットが郵送される(唾液採取または綿棒採取)。
-
検体を返送し、ラボで解析(要数週間程度)。
-
WebポータルやPDFで結果受取(遺伝的スコア、解説、参考リンクなど)。
所要時間は申し込みから結果まで4〜6週間という表示が多く、検査自体は自宅で完了する手軽さがあります。
ただし「結果をどう解釈するか」は別問題です(以下で詳述)。
サービスのプロモーション表示例や実際の所要時間は業者により異なります。
結果レポート(表示される情報の種類)
多くのGIQ系サービスが出すレポート例は次の要素を含みます。
-
総合スコア(「GIQスコア」などの独自指標)
-
学習傾向(記憶力、注意力、数学的素養、言語的素養の相対的傾向)
-
ライフスタイルや栄養、運動と結びつけたアドバイス(例:集中力を支える栄養素など)
-
科学的根拠の解説(どの研究などを参照しているかの記述)
-
利用上の注意(遺伝だけでは決まらない、環境や教育の影響も大きい、ということ)
各社のレポートは「解釈のしやすさ」や「根拠の具体性」が大きく異なります。
実物の表示は業者ごとに千差万別で、数値の出し方(標準化の仕方)なども公開されていないことがあります。
科学的な精度はどれくらい?(最新研究の要点)
科学的な精度は、重要なポイントのひとつになります。
近年の大規模研究により、知能や学力に関連する遺伝子のいくつかが同定され、集団レベルでは一定の予測力を持つ「ポリジェニックスコア(PGS)」が作成可能になりました。
しかしながら、個人のIQを高精度で予測できる段階には至ってはいないようです。
-
大規模研究は進んでおり、知能に関連する遺伝子変異の候補は増えています。が、現在のポリジェニックスコアは説明できる分散は限定的なところもあり、個人を正確に予測するにはまだまだ十分とはいえないでしょう。
-
学力・数学能力などの特定領域に結びつく遺伝的手がかりが分かり始めている研究もある一方で、環境(育児、教育、栄養、社会経済的条件など)の影響も大きく、遺伝情報だけで「この子はこれが得意/不得意」と断定することは難しいのです。

遺伝だ!とだけは言えないのですね。
-
学術界でも「ゲノムによるIQ予測にはまだ限界があり、商業化・個人向け提供に当たっては慎重な解釈が必要」という指摘が多く出てもいます。
つまり、「家庭の意思決定に直接使えるほど万能ではないけれど、研究としては進展している」というのが現状といえます。
倫理・個人情報・法的な注意点
子どもの遺伝情報の話題はとてもとてもセンシティブです。
親として検査を検討するなら、次の点を必ず確認して欲しいと思います。
自己決定権と将来の影響
子ども本人が将来自分の遺伝情報を知りたいかどうかは分からないため、親の判断で長期にわたる情報を固定化してしまうリスクがあることがあります。
データの取り扱い
業者がデータを第三者(研究機関や企業)に提供する場合があるため、同意文書の内容を精読することが必要になります。
差別やラベリング
「遺伝的に○○の傾向がある」とのラベルが教育現場や家族内で偏った期待や過小評価を生むリスクがあることがあります。
特に乳幼児期に固定観念を持つことは慎重に複合的に考える必要があるでしょう。
社会的議論
胚の遺伝子情報でIQなどを選択するサービスも報じられており、遺伝的選択の倫理は国際的な論争になってもいます。
日本国内でも臨床検査や研究での扱いに関する慎重な議論があり、実施・公開の仕方には注意が必要になることがあります。
親として受け取るべき情報の扱い方と考え方
今回、保護者支援のグループでGIQサービスの話題が出て、調べて感じたことは「データそのものはとっても興味深く、ひとつの情報として有益だけれど、結果の“商業的な見せ方”に惑わされないことが大切」という点です。

結果については慎重に受け取りたいですね。
具体的には以下の心構えをおすすめしたいと思います。
補助情報として受け止める
遺伝情報は子どもの可能性の一部を示しています。
ひとつの参考情報としては、とても有益な情報ですが、教育方針や支援の判断は「観察」「相談」「専門家の評価」をしっかりと聴くとよいでしょう。
結果を変な自信や不安の材料にしない
高スコアだったからといって過度な期待をする、または、低スコアだったからあきらめる…
ということは、どちらも避けるべきと考えます。
スコアはひとつの情報として知ることは大切ですが、環境の調整や介入で変わることもたくさんあるのです。
データ管理を徹底する
業者のデータ保存期間、第三者提供ポリシーを確認し、不要ならデータ削除を依頼して、プライバシーに配慮する必要があることがあります。
専門家に相談する
心理職、遺伝カウンセラー、小児科医や児童精神科医などと結果を一緒に見て意味を整理することもひとつの対応として推奨します。
「検査結果を基準に進路や治療の重大な決断を検査結果のみの単独で下す」のは避け、「試して情報を得る」とよいと感じています。
困ったときにはこちらも参考にしてみてください。子育て支援センターは行くべき?相談歴20年の心理師が伝える活用のメリットデメリットまとめ
まとめ:使う前に確認すべきチェックリスト
-
この検査で何を知りたいのかを明確にしましょう。
-
検査会社の根拠(参照した研究)と解釈の限界を確認しましょう。
-
データの保管期間・第三者提供・削除要請の可否をチェックしましょう。
-
可能であれば結果は専門家と一緒に解釈してみましょう。
-
倫理的な影響(家族内のラベリング、差別、自己決定権)について家族で話し合いましょう。
さいごに(親へのメッセージ)
GIQや類似の遺伝子検査は、科学の進展を反映した興味深いツールです。
ですが、「知ること」と「全てを鵜吞みにして行動すること」は別という点を忘れないで欲しいと思っています。
子どもの可能性は遺伝だけで決まるものではなく、親との愛着や環境、さまざまな学びの経験が何よりも大きな役割を果たすことがあります。
検査結果を使うときには、情報リテラシーを高く持ち、専門家と連携してよい方向に向かえるように活用したいですね。