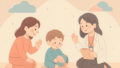はじめに

はじめての3歳児健診。何するのかな?と気になる方も多いと思います。
3歳児健診は、子どもの発育や発達を総合的に確認し、必要に応じて保護者と専門家との連携の機会になることもあります。
特に、言葉や社会性、行動面で気になることがある場合、心理師(臨床心理士・公認心理師など)との面談や相談が行われる自治体も増えています。
本記事では、3歳児健診の内容、事前準備、心理師との面談をスムーズにするコツ、相談後の対応と心構えをお伝えします。
1歳6ヶ月健診については、こちらをご覧ください。1歳6ヶ月健診の準備と発達相談ー健診相談歴20年の心理師が伝える相談のポイント

目次
- 3歳児健診とは?目的と位置づけ
- 健診でチェックされる主な項目と“発達の目安”
- 健診前の準備チェックリスト
- 心理師(心理専門職)が関わる場面とは
- 心理発達相談でよくある質問と回答準備のヒント
- 「要観察」「再検査」と言われたら/相談先の選び方
- 相談後・支援利用までの流れと注意点
- 保護者として心がけたい視点と関わり方
- まとめ:健診は育ちを見守る道標に
3歳児健診とは?目的と位置づけ
3歳児健診は、母子保健法に基づく「法定健診」の一つで、各市区町村が満3歳(満3歳を超え、満4歳に達しない幼児)を対象に実施しています。

3歳になったら全員が対象になります!
健診の目的は、健康・発育だけでなく、「発達の偏り・困りごと」を早期に発見し、必要あれば適切な支援へつなぐことです。
自治体によっては、心理職(臨床心理士・公認心理師)が健診に配置され、子どもの発達・行動面に関する相談を受け付けています。
また、3歳児健診は、乳幼児期最後の法定健診となることが多く、以降は幼稚園・保育園・学校等での発達の確認が主になります。
なので、3歳児健診は「子どもの発達を見直す大きな節目」として、意識したい機会です。

健診でチェックされる主な項目と“発達の目安”
3歳児健診では、次のような項目が総合的にチェックされます。
自治体によりプログラムや実施順序は違いますが、典型的な例を挙げています。
- 身体測定:身長・体重・頭囲・胸囲などを計測します。成長曲線との比較で発育状態を確認できます。
- 視力・聴力検査:絵を利用した視力確認や、耳元でのささやき声チェックなどがあります。家庭で一次検査を実施する自治体もあります。
- 問診・保護者アンケート:日常の発語、行動、興味・こだわり、対人関係、生活習慣などを保護者が記載します。
- 行動観察・発達チェック:当日の遊びや指示への反応、簡単な問いかけへの応答、絵本やおもちゃを使った課題などを実施することもあります。
- 内科・歯科検診:身体の健康状態、口腔・歯・かみ合わせ、口腔衛生状態などを確認します。
この中で、発達障害にかかわる可能性を検討する観点も含まれていますが、健診自体では診断を行うわけではありません。
あくまで“発達に遅れや偏りがないか見るためのスクリーニング”としての役割です。
たとえば、言葉の遅れ、対人コミュニケーションの乏しさ、同じ行動を繰り返す傾向、こだわりや極端な好き嫌い、感覚の過敏さや過敏な行動などが観察されることがあります。
これらは発達障害だけでなく、環境やストレスなどの要因も絡むため、必ずしも発達障害であるというわけではありません。

お子さんの成長を一緒に確認できる場にできるといいですね!
健診前の準備チェックリスト
- 案内・通知の確認:日時・場所・持ち物・当日の流れ・実施プログラムを自治体案内で読んでおきましょう。
- 問診票・アンケートの事前記入:普段の様子を振り返りながら事前に書いておくと、当日あわてずに済みます。
- 持ち物準備:母子健康手帳、保険証、記入済み票、朝の尿(尿検査がある場合)、替えのおむつなどが必要です。
- 子どもの体調管理:発熱・体調不良がないかを確認しましょう。健診日直前に無理なスケジュールを入れない方が安心かもしれません。
- 視力・聴力の一次検査(自治体方式):家庭で行う視力・聴力検査を求める自治体では、事前に手順が通知されることがあります。2.5m離れて絵を見せるなど、発達的な配慮も含んだ構成になっていることがあります。
- 親の心構え・メモ準備:質問したいこと・日頃気になっていることをまとめてメモしておくとよいでしょう。
特に、子ども本人のペースに配慮し、会場入り前に少し余裕を持たせたり、子どもの好きな本やおもちゃを持参したりするなど、安心感を支える準備も効果的です。

心理師(心理専門職)が関わる場面とは
自治体によっては、健診時に心理師(臨床心理士・公認心理師等)を配置し、健診中または健診後に発達面・行動面の相談を受け付けています。
心理士が関わる目的は、以下のようなものです。
- 問診票・保護者の訴えから行動・発達の傾向を把握し、懸念点を整理する
- 目の前の子どもの反応(絵・おもちゃ・指示への応答など)を観察し、発達の偏り、得意・苦手な領域を見立てる
- 保護者と面談し、日常の関わり方・家庭環境・支援ニーズを聞き取る
- 必要に応じて、地域の発達相談・専門機関への紹介・フォローアップを提案する
実際に現場で心理相談を担当する専門家は、保護者とのやりとりを重視し、「相談してよかった」という体験を提供することを意識しています。
生活のやりとりを具体的に聞き取り、それを踏まえた現実的なアドバイスを行うことを大切にしています。
心理相談で多い相談内容には、言葉・発音の遅れ、お友だちとの関わりが苦手、集団行動が苦手、気持ちの切り替えが難しい、指示理解が遅い、こだわり行動がある、感覚の過敏さ、偏食などがあります。
また、3歳時点での心理相談では、言葉の問題だけでなく、行動・性格傾向や家庭環境・親子関係の困り感を含めた相談が増えてくるという調査報告もあります。

心理発達相談でよくある質問と回答準備のヒント
心理発達相談では、保護者からの日常の気になる点や発達傾向を整理した質問が出されることがあります。
| 質問例 | 準備のヒント/ポイント |
|---|---|
| 日常で困ること・気になることは何ですか? | 事前にメモしておく。言葉・遊び・順応性・対人関係・興味行動など、具体例(いつ・どこで・どのように)を。例:「外出先で切り替えに時間がかかる」「新しい環境で緊張して固まる」など。 |
| 過去の発達歴や幼少期の特徴はどうでしたか? | 妊娠・出産・早期の成長(寝返り・はいはい・言葉の出始め)・1歳半健診など、発達軸の履歴を母子手帳や記録から整理しておくとスムーズ。 |
| 好きな遊び・興味を示すものは何ですか? | 子どもがよく遊ぶおもちゃ・テーマ(電車・お絵かき・動物など)を挙げ、それを使って関わりを促す方法も聞けるように。 |
| 指示への反応・理解はどうですか? | 「○○してね」と言った時の反応、複数行程の指示(「これを取って、それをしまって」など)の実行具合を具体的に思い出しておく。 |
| こだわりや繰り返し行動はありますか? | 特定の遊び・順番・物へのこだわり、変化を嫌う反応などを具体的に思い返しておく。 |
| 気配り・共感・対人関係の様子はいかがですか? | 友だちとの関わり、自分から声をかけるか、順番を待つ場面での行動などエピソードを準備。 |
| 親子の関係性・育てづらさについて聞かれることは? | 育児でストレスに感じる点、子どもの対応で悩んでいること、親として支えが欲しいことを正直に伝えられるよう整理。 |
こうした質問に備えることで、心理発達相談をより有意義なものにできます。メモを持参し、安心して率直に相談できる関係をつくることが大切です。

「要観察」「再検査」と言われたら/相談先の選び方
健診で「要観察」や「再検査」と指摘されるケースがあります。
これは「現時点で基準を若干外れている可能性があるから、より詳しく見る必要がある」という意味で、診断を意味するわけではありません。

不安になりすぎず。一緒に成長を応援しましょうということです。
とはいえ、早めの対応が将来の安心につながることもあります。
公認心理師ら専門家も、「早期療育」のメリットを理解していて、発達・社会性・コミュニケーション能力を伸ばす支援がより効果的になる可能性があると言われています。
相談先の選び方
- 発達相談センター・発達支援拠点:自治体が設置する拠点で、発達の専門スタッフ(心理師・作業療法士・言語聴覚士等)が対応します。
- 児童発達支援事業所・療育施設:個別・集団支援プログラムを提供する施設。体験利用や見学を行っている施設もあります。
- 小児科・発達外来クリニック:必要に応じて医学的な評価や診断、処方的支援を行える専門の医療機関です。
- かかりつけ医(小児科)・保健センター:日常の成長観察をしてきた医師や保健師に相談することも有効です。健診担当者から紹介を受ける場合もあります。
選び方のポイント
- 子どもの困りごと・気になる分野(言語・行動・発達など)を基に専門性を持つ相談先を選ぶ。
- 対応可能年齢・待機期間などを事前に確認する。
- 見学や体験が可能な施設は、実際の雰囲気を確認して安心感を得る。
- 相談先を複数候補にしておくことで、スムーズな移行ができるようにしておく。
こちらの記事も参考にしてみてください。子育て支援センター行くべき?相談歴20年の心理師が伝える活用のメリットデメリットまとめ

相談後・支援利用までの流れと注意点
支援利用までの流れ
- 結果説明・助言の受け取り:心理師から発達傾向・強み・支援が必要と思われる点などの見立てと、家庭での関わり方アドバイスを受けます。
- フォローアップ観察・記録:日常での変化を記録し、支援利用のタイミングや効果を見極めます。「できるようになったこと」「困ったこと」を記録しておくと役に立ちます。
- 支援機関への申請・利用開始:発達支援拠点や療育施設へ通う場合、自治体への申請や利用手続きが必要になることがあります。支援契約・サービス内容を確認してから利用を開始しましょう。
- 定期的な見直し・相談継続:支援内容や子どもの発達に応じて、プログラム調整・別の専門機関への紹介が行われることもあります。
支援利用の注意点
- 支援は「万能」ではない。子ども一人ひとりの特性に合わせた支援が重要。
- 待機期間や定員制の施設が多いので、早めに動いておくとよい。
- 家庭・園・支援機関間で情報共有をすることで一貫性のあるサポートを。
- 親自身の疲れ・メンタルにも配慮し、支援を必要なら受ける体制を整えておく。
保護者として心がけたい視点と関わり方
3歳児健診・相談をきっかけに、子どもの発達・気持ち・関わり方を見つめる良い機会となります。
次のような視点を持つことが、子どもの安心感と伸びを支えるヒントになります。
- 比較より“その子らしさ”を大切に:他の子と比べず、その子のペース・興味・得意を見守ってみましょう。
- 小さな“できた”を丁寧に認める:少しの進歩・挑戦を日常で見つけ、働きかけを褒めてみましょう。
- 関わりを楽しむ:指示や修正ばかりでなく、子どもの興味に乗る、共遊び・やりとりを通じて育むことを楽しんでみましょう。
- 環境の配慮を意識する:余裕時間・刺激の少ない空間・視覚的なサポート(イラスト・予告)など、小さな工夫で安心感を高められます。
- 支援・相談は“後ろめたさ”を感じずに:気になる点は早めに相談してよいのです。支えを得ることは子どもの未来への投資です。
親自身のストレスや悩みを一人で抱え込まず、家族・相談機関・オンライン支援なども活用していくことも大切です。

親御さんも自分の毎日を誉めましょうね、よく頑張っています!
まとめ:健診は育ちを見守る道標に
3歳児健診は、健やかな発育と発達を確認するだけでなく、子どもの発達を支える仕組みと連携を始める大切な機会です。
「要観察」「再検査」と言われたからといってあわてず、支援や相談体制を知っておくことで、安心して次の一歩を踏み出せます。
子どもの成長は日々変化します。小さな一歩を見逃さず、理解を持って育ちを支えていけるよう、ぜひこの健診を“子どもとあなたの未来をつなぐ出発点”としてみてください。
健診当日・相談後の記録(発語の変化・行動パターン・興味変化など)を、スマホノートや育児ノートに残しておくと、後から支援機関とのやりとりにも活きてくることがあります。

社会の皆でお子さんの育ちを支えていけるといいなと思っています。